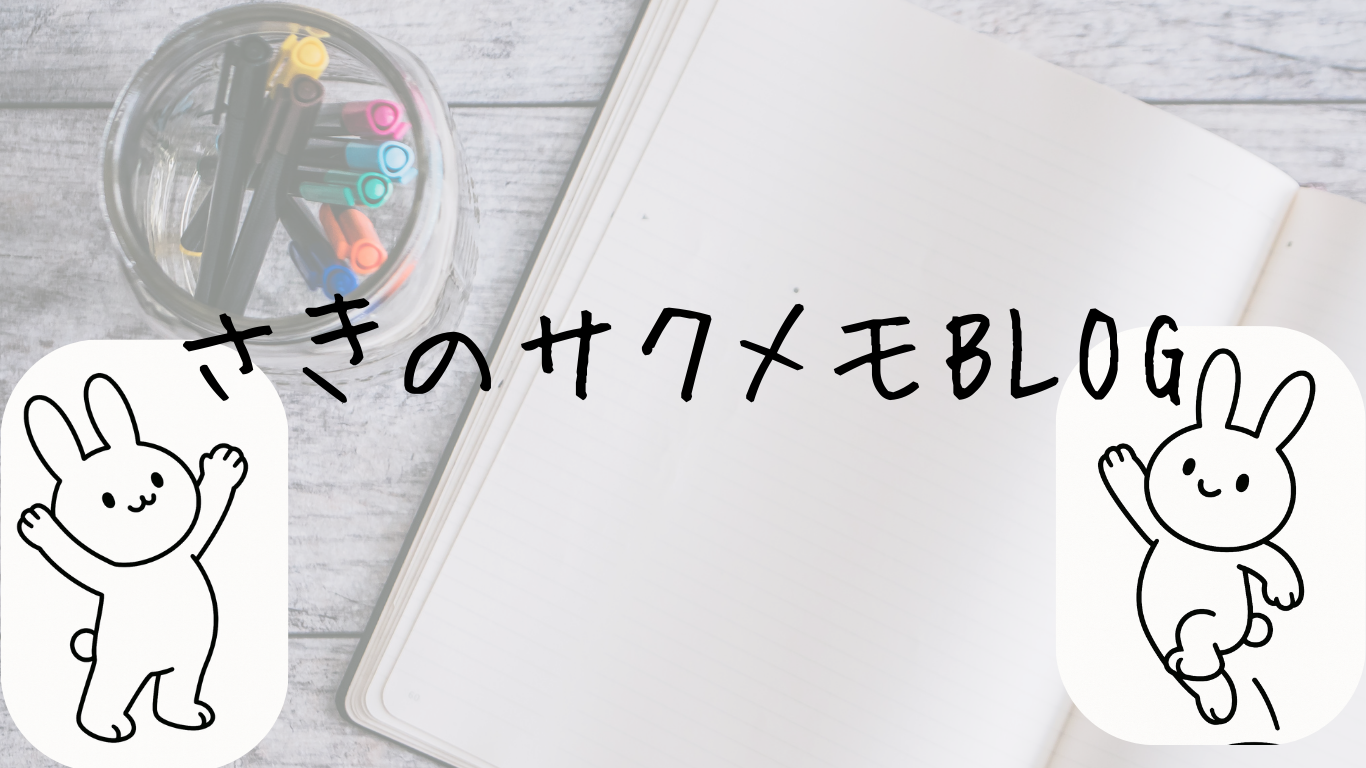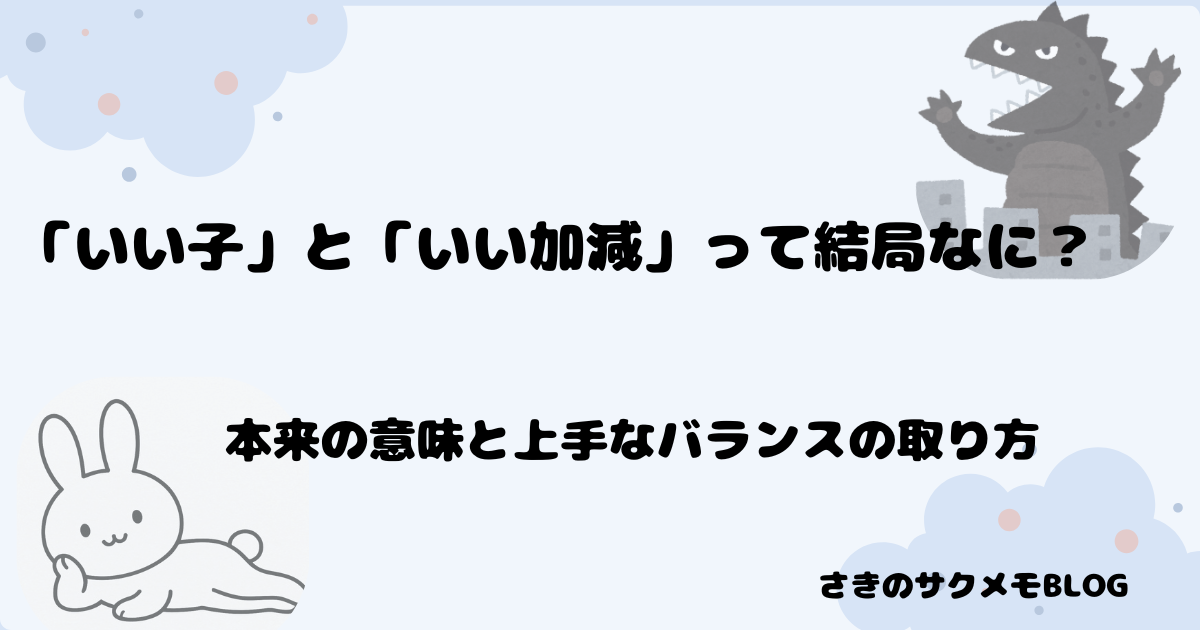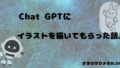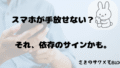その言葉、ちょっと重くない?

「いい子だね」って言われると、くすぐったいような、ちょっと背筋が伸びるような気持ちになりますよね。
一方で「いい加減にしなよ」と言われると、胸にグサッと刺さります・・・。
どっちも日常でよく聞く言葉だけど、受け取り方や使い方で、心の重さが全然ちがうんです。
今回はこの2つの「いい子」と「いい加減」を、自然体でほどきながら本来の意味と上手な距離感を一緒に探っていきます。
「いい子」って、ほんとはどんな子?
ざっくり言えば「周りから見て望ましい行動をする人」。
礼儀正しい、約束を守る、思いやりがある。どれも素敵なことです。だから「いい子」であること自体は悪くない。むしろ社会では信頼の源になります。
ただ、ここに落とし穴。
“いい子でいなきゃ”が強くなりすぎると、自分の気持ちを置き去りにしやすいんです。
- 期待に応えることが最優先になって、本音が見えにくくなる
- 「NO」が言いづらく、頼まれごとを抱え込みがち
- ほめられるために頑張り続けて、心が疲れる
だからこそ、「いい子」を続けるほど、自分の気持ちを見失わない小さな習慣が大切になります。
いちど深呼吸。「いい子」を軽やかに保つコツ
- 本音を短く伝える練習…「今日は無理」「明日はOK」など、短文で十分。
- “自分の納得”で動く比率を上げる…褒められるためではなく、やってみて気持ちいいからやってみようと思う気持ちが大事。
- 失敗OKの場所をつくる…完璧じゃない自分を許すリハビリ。家ノートや気心知れた人との会話でも。
「いい加減」の本来の意味は“ちょうどいい”
「いい加減にしろ!」の強い口調のせいでネガティブに聞こえがち。
筆者は、【いい子】ではなく【いい加減】の人ですよ。
本来の「いい加減」は、ほどよい・適度・バランスが取れているというポジティブな言葉です。(し、知らなかった・・)
- 「お風呂の湯加減がいい加減」= 熱すぎずぬるすぎず、気持ちいい温度
- 「味つけがいい加減」= 濃すぎず薄すぎず、ちょうどいい
- 「肩の力を抜いていい加減にやろう」= 力みすぎず、ほどよい力感で
「いい加減」は丁寧さを捨てる合図ではなく、過不足のない心地よさ。
ここ、誤解されがちなので覚えておくとラクになりますよ(きっと)。
なぜネガティブにも聞こえるの?
同じ言葉でも、文脈が変わると意味が反転します。
- 「仕事がいい加減だ」= 無責任/粗い
- 「説明がいい加減だった」= ざっくりしすぎ/雑
- 「いい加減にして」= もう限界、ストップの合図
ポイントは、“程度の話をしているのか/態度を責めているのか”。ここを聞き分けると、コミュニケーションのすれ違いがぐっと減ります。
「いい子」と「いい加減」——うまい距離感の作り方
いい子=人との関係のバランス。
相手の期待も大事、自分の気持ちも同じくらい大事になってきます。。
いい加減=物事の程度のバランス。
力を入れすぎず、抜きすぎず、ちょうどよく。
どちらもキーワードは「行き過ぎない」。白黒の間に、自分に合うグレーを見つける作業です。
明日から使える小さな具体例
- 予定の返事:「行きたいけど今日は体力不足。別日ならいける」→ いい子すぎず、断りきれずでもない。
- タスク管理:90分全力より、25分集中+5分休憩×3のいい加減サイクル。
- 家事の基準:完璧清掃より「床がサラッとしてればOK」のいい加減を決める。
- 人の頼み:「今日は2件まで手伝う。3件目は明日」→ 自分も相手も守る線引き。
まとめ:言葉に引っ張られすぎない
「いい子」は、あなたの誠実さの表れ。でも、本音の自分を置き去りにしないでください。
「いい加減」は、本来“ちょうどいい”。手抜きの合図じゃなく、あなたを長く守るためのリズム。
背伸びもしない、投げやりにもならない。今日の自分に合ったいい加減で、いい子となりませんか?
あなたの「ちょうどいい」が、見つかりますように。