「暑さ寒さも彼岸まで」って、一度は聞いた言葉じゃないでしょうか?
春分や秋分の時期になると、続いていた厳しい暑さや寒さがようやく落ち着いてくる。そんな季節の変化を表す昔ながらの言葉です。
でも、この言葉はただ、天気の話にとどまらず日本の自然観や人生観、そしてちょっとした生き方のヒントまで含んでいると言われています。
季節の変わり目と日本人の感性

日本は四季がはっきりしていて、その移り変わりを敏感に感じ取って暮らしてきた歴史があります。ただ、今年は秋が来るのが遅いのか9月でも暑い日が続いています。
春分と秋分の時期は昼と夜の長さが同じになり、自然のバランスがちょうどいい時期なんです。だから、昔の人にとって彼岸のタイミングは特別な節目だったんですね(/・ω・)/
困難もいつか終わる。人生の比喩
「暑さ寒さも彼岸まで」には、もう一つの大切な意味があります。
それは、「大変なことも、いつか終わる」という人生の教えです。
例えば、仕事のストレスや人間関係の悩み、健康の不安など・・。
生きていればいろいろな困難にぶつかります。
ですが、「暑さ寒さも彼岸まで」って言葉を思い出すと
「このしんどさも、いずれ落ち着く日が来る」と前を向ける気がしませんか?
自然のリズムと人生の浮き沈みを重ね合わせることで、昔の人は心の支えにしてきたんですね。
仏教と彼岸。精神的な意味合い

彼岸という言葉は、仏教からきています。
現世の苦しみや迷いに満ちた世界を【此岸(しがん)】
悟りの境地を【彼岸(ひがん)】
と呼びます。
春分と秋分の時期を彼岸としたのは、昼夜の長さが同じ=中道の精神を表しているから。
日本では個々に先祖供養の文化が重なり、お墓参りをしたり家族で集まったりする風習が定着しました。現代でも、お彼岸にお墓参りに行く家庭は多いですよね。静かな時間の中でご先祖に手を合わせると、日常の喧騒から少し距離をとれて心が落ち着きます。
(筆者は、ここ数年お墓参りに行っていないので・・彼岸中の間にお墓参りに行きたいと思っております・・。)
現代だからこそ響く言葉
今年は、気候変動が多く体にも多くの負担がかかっていることや、ストレス社会といった現代の問題にこそ、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉は意外とマッチします。自然の移ろいや季節のリズムを意識することは、心のゆとりにも繋がり環境への意識を高めるきっかけにもなります。
便利さや効率を求める生活の中で、昔ながらの言葉が思い出させてくれるのは「待つこと」「流れに委ねること」の大切さなのかもしれませんね(*´ω`*)
まとめ
「暑さ寒さも彼岸まで」は、
- 季節の変わり目を表す言葉であり
- 人生の困難もやがて終わるという希望のイメージであり
- 仏教や日本文化と深く結びついた表現
なんです。
デジタル社会のいま、こうした昔の言葉が持つ自然との調和や心の余裕を、もう一度見直してもいいかもしれませんね。
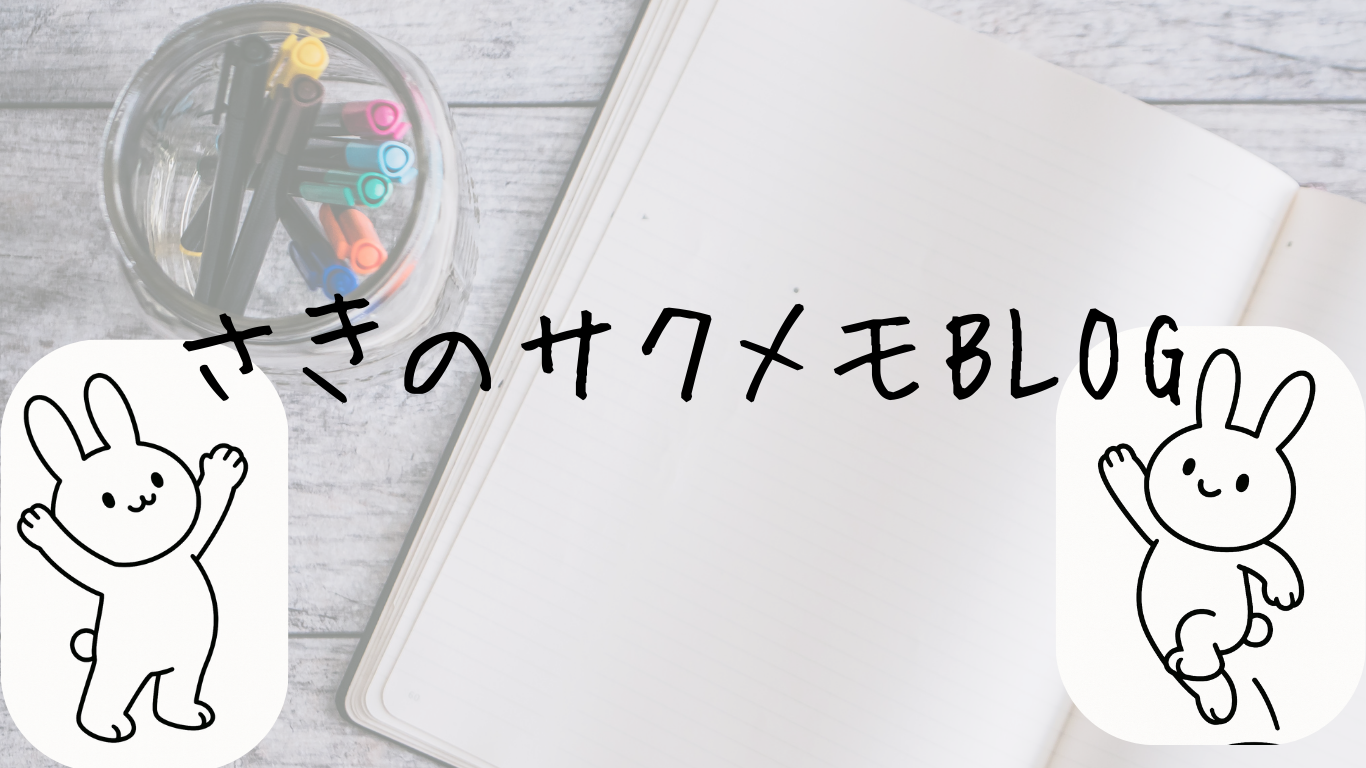


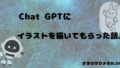
コメント